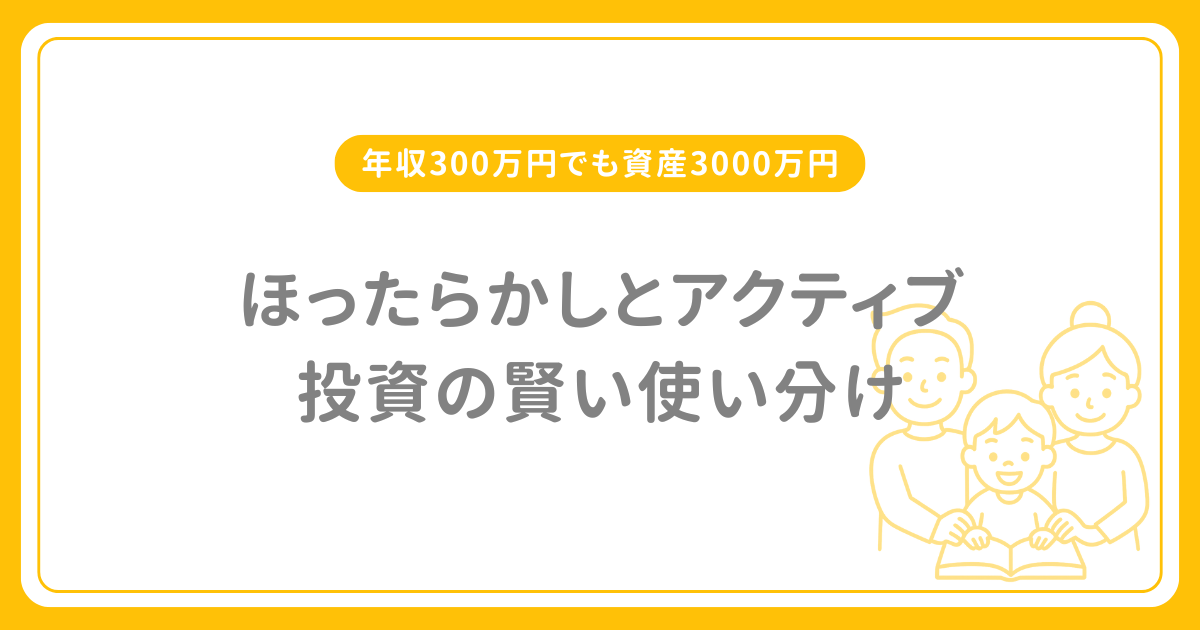「投資を始めたいけど、どんな方法が自分に合っているのか分からない…」
「忙しくて毎日株価をチェックする時間なんてない」
「でも、ただ銀行に預けているだけではお金が増えないのも不安」
こんな悩みを抱えていませんか?
この記事では、投資初心者や子育て世代にも取り組みやすい「ほったらかし投資」と、積極的に利益を狙う「アクティブ投資」の特徴と違いをわかりやすく解説します。
さらに、両者を組み合わせることで得られるメリットや、筆者自身のポートフォリオも公開。
実践的なステップも紹介するので、投資経験ゼロでも安心して始められます。
私自身もiDeCoや新NISAで「ほったらかし投資」を続けつつ、余裕資金で個別株や暗号資産に挑戦し、資産を3,000万円以上に増やすことができました。
この記事を読み終えるころには、あなたも「守り」と「攻め」を組み合わせ、自分に合った投資スタイルを選べるようになっているでしょう。
まずは気軽に読み進めて、投資の一歩を踏み出してみませんか?
【ほったらかし投資】と【アクティブ投資】の特徴
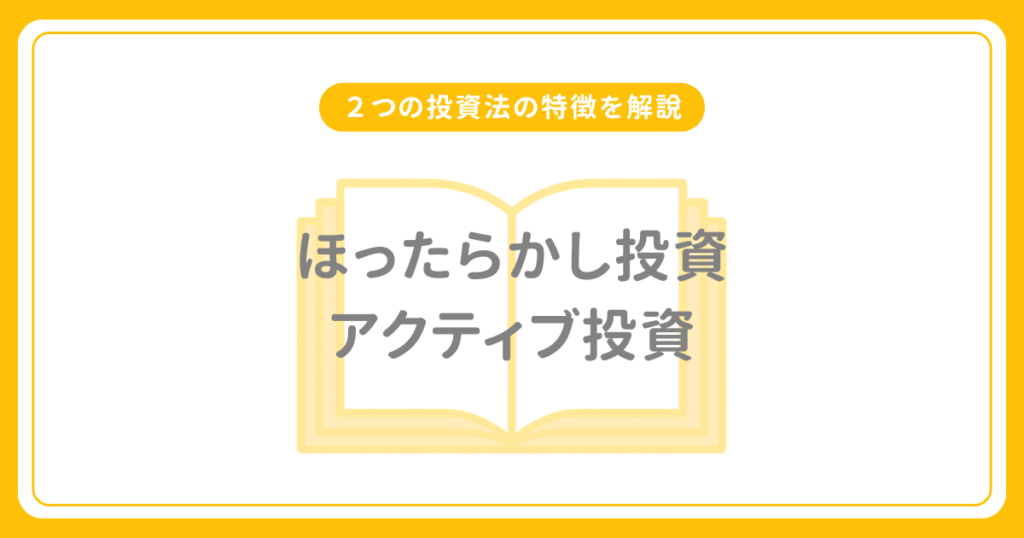
投資の世界には、様々な方法がありますが、大雑把に分けると「ほったらかし投資」と「アクティブ投資」の二つのタイプに分類できます。
まずは、それぞれの特徴を理解することから始めましょう。
ほったらかし投資とは?
文字通り、一度設定したら、後は基本的に何もせずに運用を続ける投資手法です。
頻繁に売買したり、市場の動きを常にチェックしたりする必要がないため、忙しい子育て世代でも無理なく続けられます。
ほったらかし投資の一番のメリットは、手間がかからないことです。
一度設定すれば、後は自動で積み立ててくれるため、忙しい子育て世代に最適な方法となります。
また、インデックス型投資信託を選べば、運用コストを抑えたうえで、数百から数千もの銘柄に分散投資をすることができるため、リスクを抑えた運用を行うことが可能です。
それを自動で積み立てていれば、市場が一時的に下がっても、慌てて売却するような感情的な判断を防ぐこともできます。
一方、ほったらかし投資のデメリットは、「市場平均以上の大きなリターンは期待しにくい」、「面白みに欠けると感じる」ことです。
あくまで市場全体の動きに連動することを目指すため、短期間で資産が倍になるようなことは基本的にありません。
自分で銘柄を選んだり、売買のタイミングを考えたりする「投資している感」が薄いため、ほったらかし投資は本当に退屈です。
しかし、「投資をしているのが退屈である状態」というのは決して悪い状態ではありません。
皆さんは、世界三大投資家の一人「ジョージ・ソロス」の名言の一つに『良い投資とは退屈なもの』というものがあるのはご存じでしょうか?
加えて、ジョージ・ソロスは『もし投資が面白くて、楽しいのならば、おそらくお金を作り出すことは出来ない。』とも言っています。
私自身、この言葉にとても共感しており、ほったらかし投資を続けるうえで常に心に留めています。
ルールを決めてコツコツと運用する「退屈な投資」こそ、長く安定した成果を出す秘訣と言ってもいいでしょう。
筆者の実践例
私の「ほったらかし投資」の中心は、iDeCoと新NISA(つみたて投資枠)でのインデックス型投資信託の積立です。
iDeCoは、簡単にいうと「国が用意してくれた老後資金づくり専用の貯金箱」のようなものです。
掛金は全額所得控除、運用で増えた分も非課税、さらに受け取るときにも税金の優遇があります。
しかも、私には「老後のお金を貯める」という明確な目的があるので、老後資金は迷わず「iDeCoでほったらかし投資」にしました。
今は毎月決まった金額を、「S&P500(米国株式)」と「金」のインデックスファンドに自動で積み立てる設定にしています。
新NISAは、2024年に非課税で投資できる枠が大幅に拡大され、資産形成の強い味方となりました。
つみたて投資枠で、こちらもS&P500や金といったインデックスファンドに毎月自動積立しています。
これも一度設定すれば後は自動なので、文字通り「ほったらかし」です。
非課税で長期的にコツコツ増やせる、これほどありがたい制度はありません。
これらの投資は、毎日のように運用状況を見たりはしません。
年に一度、または数か月に一度、「どれくらい資産が増えたかな?」と軽く確認する程度です。
だからこそ、忙しい子育て世代でも無理なく続けられるのです。
アクティブ投資とは?
市場の平均的なリターンを目指す「ほったらかし投資」に対し、アクティブ投資は市場平均を上回るリターンを目指して、積極的に運用する投資手法です。
アクティブ投資の一番のメリットは、市場平均以上の大きなリターンが得られる可能性があることです。
自分の分析や判断が当たれば、短期間で大きな利益を得られることもあるでしょう。
また、企業について調べたり、経済ニュースを読んだりするのが好きな人にとっては、知的好奇心を満たしながら取り組めますし、投資対象について調べる過程で、自然と経済やビジネスの知識が深まるという点でメリットになり得ます。
一方、アクティブ投資の一番のデメリットは、損失リスクが高いことです。
市場平均を上回るリターンを目指すということは、それだけリスクも高くなるということです。
自分の判断が外れれば、大きな損失を出す可能性もあります。
一般的に、市場平均に勝つのは難しいとされていますので、アクティブ投資の難易度は非常に高いと考えておいた方がよいでしょう。
また、自分で情報収集し、分析し、売買の判断をする必要があるため、子育て世代にとって大きな負担になる可能性があります。
時間的な負担や感情的な負担を抑えるために、アクティブ型投資信託を選択した場合も、専門家が運用するため手数料が高いことが多いですし、インデックスファンドに勝てるファンドは少ないため、これもまた難易度高めです。
筆者の実践例
私の「アクティブ投資」は、主に個別株投資と暗号資産投資です。
以前は、アクティブ投資信託にも投資をしていましたが、成績が振るわなかったため、全て解約しました。
個別株投資については、自分が応援したい企業や今後の成長に期待できると感じる企業の株を現在、合計約500万円分(金融資産の約15%)保有しています。
2018年~2025年5月末までに利益を確定させた金額は、合わせて3,294,178円です。
毎日株価をチェックするわけではありませんが、企業のニュースや決算情報は見るようにしていますし、売買の判断も自分で行っています。
自分が興味のある企業に実際に投資することで、経済の動きを自分ごととして捉えられるようになり、ものすごく勉強になりました。
企業について調べたり、経済ニュースを読んだりするのが好きな人は、少額でもいいので、無理のない範囲でぜひ挑戦してみましょう。
暗号資産投資については、非常に価格変動リスクが高い資産ですが、将来性を感じているため、現在ポートフォリオの約25%の割合で組み入れています。
現在の私の副業である「暗号資産のエアドロップ」は、特定のプロジェクトのテストに参加したり、サービスを利用したりといった「行動」によって暗号資産を得る機会を狙うものです。
保有している暗号資産を異なるチェーン同士で移動(ブリッジ)させたり、DEX(分散型取引所)において交換(スワップ)や流動性提供を行ったりして、その労働対価としてエアドロップを獲得するのですね。
これは情報収集やリスクを負った作業が必要であり、エアドロップ獲得が成功するかどうかも不確実なので、まさに「アクティブ」な取り組みだと考えてよいでしょう。
エアドロップで得た暗号資産をそのまま保有したり、余裕資金で主要な暗号資産を少額購入したりもしていますが、これも常に情報にアンテナを張り、リスクを理解した上で行っています。
アクティブ投資は、時間や知識、そしてリスクを取る覚悟が必要ですが、うまくいけば大きな利益が期待でき、さらに経済や新しい技術を深く学べる点でとても魅力的です。
もし、あなたが個別株やアクティブ型の投資信託、暗号資産などに取り組む時間と知識を確保できるなら、まずは少額から始めてみるのがおすすめです。
少額でリスクを抑えていけば、投資に失敗して市場から退場することもなく、日常生活に影響を与えることもありません。
興味がある方は、ぜひチャレンジしてみてください。
両方を組み合わせるメリットとは?
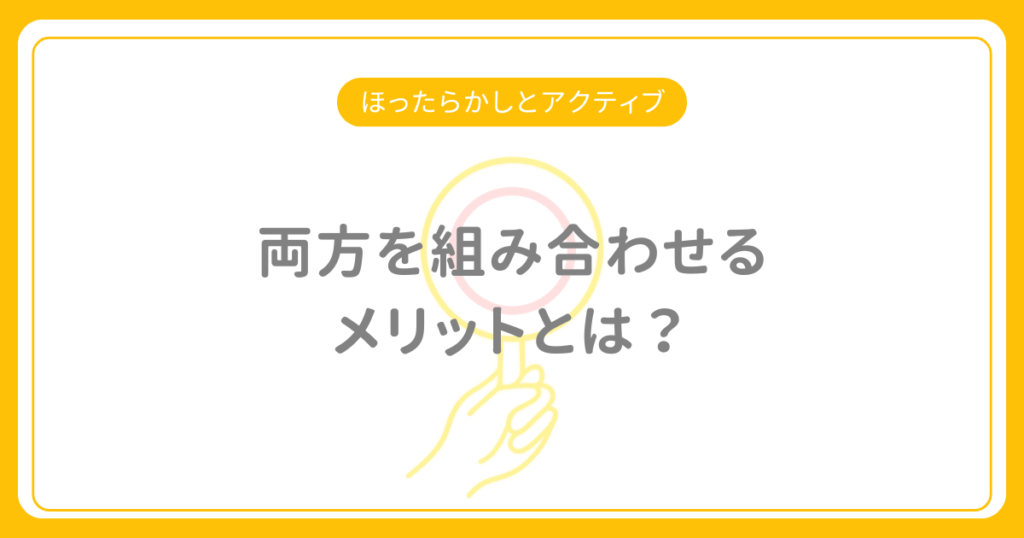
これまで見てきたように、「ほったらかし投資」と「アクティブ投資」には、それぞれにメリットとデメリットがあります。
私の経験からお伝えすると、この2つはどちらか一方に偏るのではなく、両方を組み合わせて使うのがベストです。
なぜなら、両方を組み合わせて上手に使い分けることで、リスクとリターンのバランスを取り、安心感を持ちながら資産を増やせるからです。
片方だけに頼るとどうなる?
例えば、資産をすべて「ほったらかし投資」にすると、市場全体の平均的なリターンしか得られません。
これは堅実ですが、「もっと早く資産を増やしたい」と思う人にとっては物足りなさを感じるでしょう。
逆に、資産のすべてを「アクティブ投資」にすると、価格の上がり下がりが大きく、損失が出た時に精神的なダメージも強くなります。
特に初心者にとって、この不安は大きな負担となるでしょう。
バランスの取り方のイメージ
先ほども言いましたが、資産の大部分は「ほったらかし投資」でコツコツ安定的に増やしつつ、一部は「アクティブ投資」で成長を狙うという組み合わせが理想です。
こうすることで、「退屈でも安定的に増えるお金」と「挑戦的で成長を狙うお金」を同時に持つことができます。
結果として、全体のリスクを抑えながら資産の増加スピードを高めることが期待できるのです。
資産形成の初期段階は【ほったらかし投資】のみがおすすめ
ここまで、「ほったらかし」と「アクティブ」は両方を組み合わせて運用するのが良いとお伝えしてきました。
ただし、資産形成を始めたばかりの段階では、まだ「アクティブ投資」に取り組む準備ができていない方が多いと思います。
そのため、投資をスタートしたばかりの初心者や、まだ資産が少ない時期は、まずはリスクを抑えてコツコツ資産を増やすことを優先しましょう。
資産がある程度増え、お金や投資の知識も身についてきたら、「失っても生活に影響しない少額」で「アクティブ投資」に挑戦するのがおすすめです。
私自身も最初は、投資の知識がほとんどなかったので、iDeCoやつみたてNISAを使った「ほったらかし投資」だけを行っていました。
その後、副業収入が増えてきた頃から、少しずつ個別株や暗号資産などに投資を始めていきました。
「守り」のほったらかしと「攻め」のアクティブを上手に使い分ける
「ほったらかし投資」は、いわば資産の「守り」です。
株や債券などに幅広く分散して投資し、長い時間をかけて安定した成長を目指します。
これは、教育資金や老後資金といった「絶対に減らしたくないけれど、着実に増やしたい大切なお金」にぴったりの方法です。
一方で、「アクティブ投資」は、資産の「攻め」の部分です。
自分で特定の株やテーマを選び、市場の平均より大きな利益を狙うのです。
これは、多少のリスクをとっても良い「挑戦用のお金」で行えば、全体の資産を大きく伸ばす可能性を高めることが期待できます。
このように、「守りのほったらかし」と「攻めのアクティブ」を組み合わせることで、自分のリスクの許容度や目標に合わせて全体の資産バランスをコントロールできます。
そうすれば、不安を抑えながら効率よく資産を増やすことができるのです。
【筆者公開】「私のポートフォリオ」と考え方
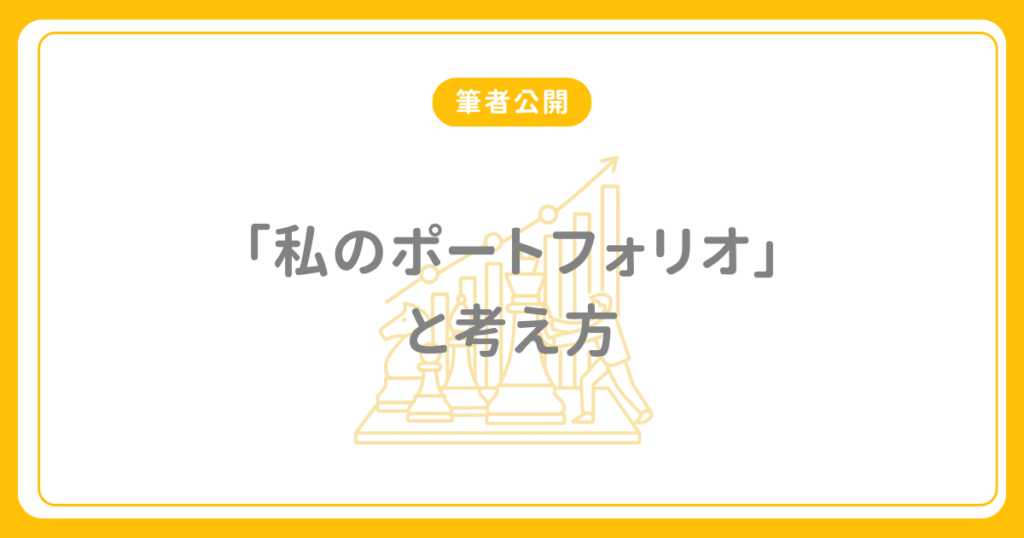
では、実際に私がどのような割合で「ほったらかし投資」と「アクティブ投資」を使い分けているのか、私の現在のポートフォリオ(資産の内訳)とその考え方を公開します。
私の現在の純資産約3,150万円の内訳は、ざっくりと以下のようになっています。
見ていただくと分かるように、資産の約20%を現預金、約34%を「ほったらかし投資」が占めています。
これが私の資産形成の土台であり、「守り」の部分です。
その上に、リスクは理解しつつ「攻め」のアクティブ投資を乗せているイメージです。
それぞれの項目について、もう少し詳しく説明していきましょう。
現預金(約20%)
これは、「生活防衛資金」と「株や投資信託を買うための余力」となります。
「生活防衛資金」は、日々の生活費や、緊急時(病気や失業など)に備えるための資金です。
投資に回してしまうと、いざ必要になった時にすぐ使えなかったり、市場が下がっていて損をしたりするリスクがあるため、投資資金とは分けて、いつでも引き出せる銀行預金で確保しています。
目安としては、生活費の3ヶ月~1年分と言われますが、私は1年分の300万円を確保しています。
「株や投資信託を買うための余力」は、『市場暴落時』や『監視している個別株が買える水準に落ちてきたとき』などに備えるための資金です。
チャンスが来たとき、すぐ動けるように証券口座で確保しています。
ほったらかし投資(約34%)
これが、私の資産形成の「核」です。
具体的には、iDeCoと新NISA(つみたて投資枠 + 成長投資枠の一部)で運用しているインデックス型投資信託がほとんどを占めます。
まず、iDeCoでは、毎月5,000円を全米株式と金のインデックスファンドに自動で積立投資しています。
これはもう、文字通り老後まで「ほったらかし」です。
節税メリットが大きいため、老後資金のために最優先で取り組んでいます。
新NISAのつみたて投資枠では、毎月3.3万円を全米株式などの低コストで広く分散されたインデックスファンドに自動で積立投資しています。
これも一度設定すれば自動で買い付けられるため、「ほったらかし」ですね。
子供の教育費や住宅購入頭金などのために、コツコツ資産を増やすための主軸となっています。
新NISAの成長投資枠では、つみたて投資枠では購入不可能な投資信託、例えば「金(SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド・為替ヘッジなし)」などの積立を行い、残りを単発で購入する投資信託や後述する個別株投資に充てています。
成長投資枠で積み立てているインデックスファンドの部分も、基本的には「ほったらかし」運用です。
アクティブ投資(約46%)
アクティブ投資は、市場平均以上のリターン、新しい分野への挑戦を目指す「攻め」の部分です。
具体的には、個別株投資と暗号資産投資がこれにあたります。
個別株投資では、全体の資産の一部(約15%程度)を成長に期待する国内個別株に投資しています。
購入したら基本は長期保有ですが、企業のIR情報などをチェックしたり、買い増しや売却を検討したりする可能性があるので、アクティブに分類しています。
暗号資産は、2024年11月時点で全体の資産の約30%程度を占めています。
暗号資産の比率が多いと感じられるかもしれませんが、USDCなどのステーブルコイン(米ドルに連動する暗号資産)が暗号資産全体の40%程度を占めていますので、実際のリスク資産の比率は約18%です。
これらのリスク資産には、エアドロップで得たものや、自分で購入したもの(ビットコイン、イーサリアムなど)が含まれます。
そして、暗号資産市場は価格変動が非常に大きく、リスクも高いことを理解しているため、失っても生活に影響しない金額に限定しています。
エアドロップ狙いの活動は、情報収集や日々の作業が必要なので、これもアクティブな取り組みです。
成功すれば一時的に資産が大きく増える可能性はありますが、不安定な収入源・資産と考えています。
ポートフォリオの考え方と変遷
このポートフォリオは、最初からこの割合だったわけではありません。
資産形成を始めた2018年頃は、貯金500万円がありましたが、そこからまず始めたのはiDeCoとNISAでの積立(ほったらかし投資)だけでした。
個別株や暗号資産にはまったく手を出していません。
家計管理を徹底し、毎月の余剰資金をコツコツとiDeCoとNISAに回す、これが初期の私の戦略でした。
まずは「守り」で、資産の土台を築くことに集中したのです。
その後、資産が少しずつ増え始め、お金や投資に関する知識も深まってきた頃から、「もう少しリスクを取って、リターンを狙ってみても良いかな」と考え始めました。
その頃、副業収入も徐々に増えてきていましたので、「攻め」の投資資金としてそれを充てたいという考えも強くなっていました。
そこで、資産のごく一部を「個別株投資」やリスクは高いけれども将来性に期待できる「暗号資産」に回すことにし、「アクティブ投資」を開始したという流れです。
今ではこのような、「ほったらかし」を核とし、「アクティブ」をスパイスのように加える使い分けが私にとって最も心地よく、資産形成を加速させてくれた最高のバランスだと感じています。
私のポートフォリオを見て、「自分にもできるかも?」と感じていただけたら嬉しいです。
【初心者向け】無理なく始める4ステップ
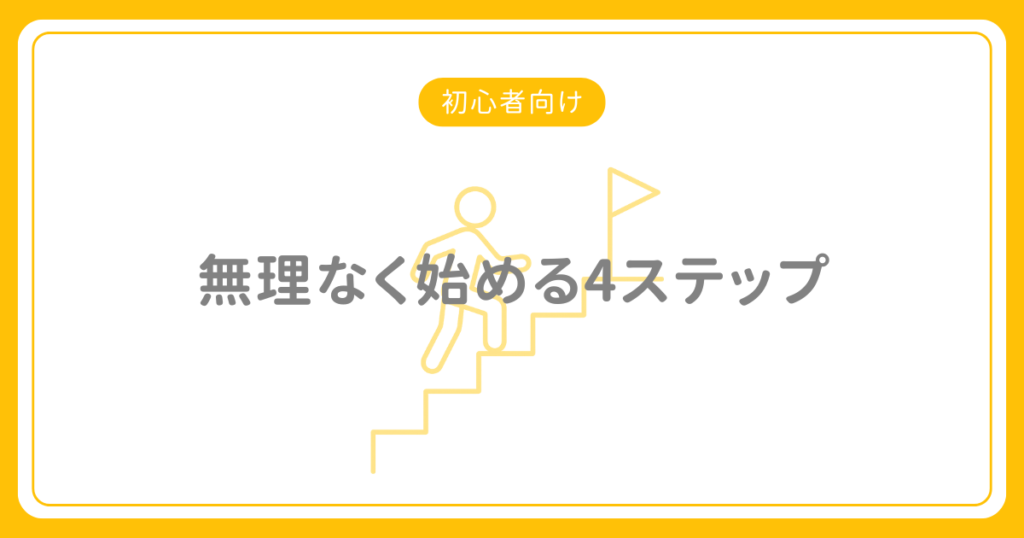
ここからは、投資初心者の方でも「ほったらかし」と「アクティブ」の使い分けを無理なく始めるための具体的なステップをご紹介します。
具体的なステップは、以下の通りです。
では、それぞれについて説明していきしょう。
まずは家計を把握し、投資に回せる「余剰資金」を知る
どんな投資を始めるにしても、まず最初にやるべきことは、あなたの家計の状況を正確に把握し、投資に回せる「余剰資金」を知ることです。
なぜなら、無理な金額を投資に回すと生活が苦しくなったり、一時的に資産が減った時に精神的に耐えられなくなった場合、冷静な判断ができなくなるからです。
投資は、生活に必要なお金とは別に「なくなってもすぐに困らないお金」で行うのが鉄則です。
家計の見える化
家計簿アプリ、エクセル、手書きノートなど、あなたが続けやすい方法で構いませんので、まずは1ヶ月、できれば3ヶ月分の収入と支出を全て記録してみましょう。
「何に」「いくら」使っているのかが分かると、どこに無駄があるのか、どこを改善できるのかが見えてきます。
「お金の健康診断」ですね。
私も、家計簿アプリ(マネーフォワードME)で毎月の収支を記録し、数ヵ月に一度は見直す習慣をつけています。
最初は手間だと感じましたが、これが投資に回せるお金を捻出する第一歩でした。
最初の数ヵ月の記録を見直しただけで、医療保険や携帯代、サブスクリプションなど合計で『年間20万円』の無駄な支出を改善することができたことはとても嬉しかったです。
生活防衛資金を確保する
次に、 緊急時に備えるための「生活防衛資金」を、投資資金とは別に銀行預金などで確保しましょう。
これは、『病気で働けなくなった』、『会社を辞めることになった』といった事態に備えるためのお金です。
目安は、一般的に生活費の3ヶ月~1年分と言われます。
ご自身の家族構成や働き方(共働きか、片働きか)、会社の安定性などを考慮して、安心できる金額を設定しましょう。
この生活防衛資金が貯まるまでは、投資よりも貯金を優先することをおすすめします。
私の場合、貯金300万円(1年分の生活費)を生活防衛資金として貯金していました。
このように、家計を把握し、生活防衛資金を確保した上で、「毎月〇円なら投資に回せそうだ」「ボーナスが出たら〇円を投資に回せる」といった具体的な余剰資金の額を把握することが重要です。
それが、投資のスタート地点となります。
「ほったらかし投資」を始める
投資に回せる余剰資金が分かったら、いよいよ投資開始です。
投資初心者の方、特に子育て世代には、まず「ほったらかし投資」から始めることを強くおすすめします。
なぜなら、「ほったらかし投資」は、次のような初心者にとって非常に取り組みやすいメリットがあるからです。
新NISAを活用する
2024年から始まった新しいNISAは、非課税で投資できる金額(年間最大360万円、生涯最大1800万円)と期間が無期限になり、非常に使い勝手が良くなりました。
特につみたて投資枠は、毎月コツコツ積み立てるのに向いています。
対象商品も、手数料が安く、長期の資産形成に向いているインデックス型投資信託などに限定されています。
始める手順は、以下の通りです。
新NISAを始める手順
- 証券会社を選ぶ
- NISA口座を開設する
- 投資する銘柄を選ぶ
- 積立設定をする
①証券会社については、ネット証券(SBI証券、楽天証券、マネックス証券など)が、手数料が安く、取扱銘柄も豊富でおすすめです。
銀行でも開設できますが、商品ラインナップや手数料で劣ることが多いため、おすすめできません。
②NISA口座の開設については、証券会社のサイトから申し込みできます。
マイナンバーカードが必要ですから、事前に取得しておきましょう。
口座開設の開設の手続き自体はそれほど難しくありませんが、不備などで少し時間がかかることもありますので、気長に待ちましょう。
NISAの口座開設が完了したら、③投資する銘柄を選びましょう。
つみたて投資枠なら、手数料(信託報酬)が低く、全世界の株式やアメリカの主要企業(S&P500など)に幅広く分散投資できるインデックスファンドがおすすめです。
私は、「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」といった銘柄を中心に積み立てています。
④積立設定は、毎月いくら積み立てるか、引き落とし日はいつかなどを設定しましょう。
銀行口座からの自動引き落としや、クレジットカードでの積立も可能です。
一度設定すれば、後は自動で買い付けが行われるので、「ほったらかし」が実現できます。
簡単ですね。
新NISAについて、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にするとよいでしょう。
-
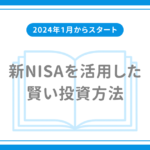
-
新NISAをフル活用!家計を豊かにするための賢い投資方法とは?
「投資って難しそう…」「損するのが怖いな…」 そんな風に思う一方、将来のためには「資産形成を始めなければ…」という気持ちもあるのではないでしょうか。 2024年から始まった「新NISA」は、まさにそん ...
続きを見る
第6章「新NISAの始め方」で、『口座開設~積立投資を設定まで』を詳しく解説しています。
iDeCoを活用する
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、原則60歳まで引き出せないという制約がありますが、掛金が全額所得控除になるなど、大きな税金メリットがあります。
老後資金を準備しながら節税もできる、非常に強力な制度です。
始める手順は、以下の通りです。
iDeCoを始める手順
- 運営管理機関を選ぶ
- iDeCo口座を開設する
- 毎月の掛金を設定する
- 投資する銘柄を選ぶ
①運営管理機関については、証券会社や銀行などの中から選択します。
手数料や運用商品のラインナップで比較検討しましょう。
おすすめはやはり、手数料が安く、取扱銘柄も豊富なネット証券(SBI証券、楽天証券、マネックス証券など)です。
②iDeCo口座の開設については、証券会社のサイトから申し込みでき、ネット証券においては申込から解説までWEBで完結可能です。
ただし、国民年金基金連合会などの審査が必要なため、手続き完了まで1~2ヶ月かかることがあります。
これもまた気長に待ちましょう。
③毎月の掛金は、20~65歳までの間に毎月5,000円~掛金上限額まで積立可能で、1,000円単位で自由に設定できますので、無理のない範囲で決めましょう。
④投資する銘柄は、新NISAと同様、低コストのインデックス型投資信託がおすすめです。
掛金の引き落としや商品の買い付けは自動で行われますので、iDeCoも完全に「ほったらかし」運用と言えますね。
iDeCoについて、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にするとよいでしょう。
-
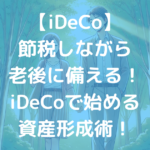
-
節税しながら老後に備える!iDeCoで始める資産形成術!
「iDeCoに興味はあるけど、仕組みが難しそう…」 「本当に始めるべき?」 「市場が暴落したらどうする?」 そんな疑問や不安をお持ちの方は少なくないでしょう。 しかし、今からコツコツと積み立てることで ...
続きを見る
第4章「iDeCoの始め方」、第5章「iDeCoの運用商品選び」で、『口座開設~商品の選び方まで』を詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
まずは、このNISAやつみたてNISAを活用したインデックス投資信託の積立という「ほったらかし投資」から、毎月5,000円や1万円といった、「この金額なら、もし減っても(あるいはなくなっても)生活には影響しない」と思えるくらいの無理のない金額で始めてみましょう。
一度設定してしまえば、後は給料天引きのように自動でお金が積み立てられていき、投資信託が自動で買い付けられます。
毎日の値動きを気にする必要はありませんので、「ほったらかし投資」は忙しい子育て世代に特におすすめです。
慣れてきたら、無理のない範囲で「アクティブ投資」を検討する
「ほったらかし投資」で資産形成の土台を築き始め、毎月の積立が習慣になってきたら、次のステップとして「アクティブ投資」を検討してみるのも良いでしょう。
ただし、ここでのポイントは「失っても生活に影響しない少額」で始めること、そして「学びの機会」と捉えることです。
アクティブ投資は「攻め」の投資であり、大きなリターンが得られる可能性がある反面、損失リスクも高まります。
だからこそ、まずは「お試し」感覚で資産のごく一部から始めてみるのが賢明なのです。
「失っても生活に影響しない少額」で始める
これがアクティブ投資に取り組む上での最も重要なルールです。
例えば、「毎月のお小遣いの範囲でやってみる」「ボーナスから〇万円だけをアクティブ投資に充てる」など具体的な金額を決めて、その範囲内で運用しましょう。
私もアクティブ投資を始めた当初、個別株や暗号資産への投資については、資産全体から見ればごく一部に留めていました。
今では、それぞれの資産が成長し、全資産に占める割合も大きくなっていますが、アクティブ投資への姿勢は当初と変わっていません。
また私のアクティブ投資は、『副業で得た収入の一部を充てています』ので、「もしダメでも本業の給料には影響しない」という安心感を持って取り組めています。
具体的なアクティブ投資の例
私たち、一般人が簡単にアクセスできるアクティブ投資は、主に以下の3つです。
個別株投資をする場合、まずは「自分が普段利用している会社の株」や「ニュースなどで見て興味を持った会社の株」を調べてみることから始めましょう。
企業について調べる過程で、経済やビジネスへの理解が深まる効果も得られます。
最近では、多くのネット証券で「単元未満株」(1株単位など、少ない金額から個別株が買えるサービス)を利用でき、数百円~数千円から投資可能なため、お試しには最適です。
私は、長期的に成長を期待できる企業を選んで、約500万円を個別株に投資しています。
頻繁に売買するわけではありませんが、情報収集は怠らないようにし、四半期決算で業績が自分の想定を下回ったときは損をしてでも売却するようにしています。
アクティブ型投資信託は、専門家が運用してくれますので、自分で個別の企業を選ぶ手間はありませんが、手数料がインデックス型より高い点に注意が必要です。
そのアクティブファンドがどのような投資を行っているか、理解できる場合のみ、投資するようにしましょう。
暗号資産投資については、繰り返しになりますが、値動きがとても激しくリスクが高い投資です。
投資するなら、「失っても仕方ないと思える金額」に限定するようにしましょう。
私がやっている「暗号資産のエアドロップ狙い」は、うまくいけば大きな利益になる可能性がありますが、その分、情報収集や手間がかかり、結果も読みにくいアクティブな取り組みです。
エアドロップ狙いを最初から取り組むのではなく、まずはビットコインやイーサリアムといった主要な暗号資産を、少額で買って値動きを体感しながら慣れていくことから始めましょう。
私の場合、一番最初にビットコインやイーサリアム、ソラナ、コスモスなどをGMOコイン(暗号資産取引所)で購入し、1年間ほど値動きを体感して慣れた後、それらの暗号資産をエアドロップ活動の原資金として充てました。
その間、購入していた暗号資産が倍以上に値上がりすることもありましたし、逆に半値以下になることもありました。
エアドロップ狙いをしている最中も、ハッキングの被害に巻き込まれたり、存在しないウォレットアドレスに誤って送金をしてしまったりして資産の一部を失うこともありました。
暗号資産投資をするときは、そのようなリスクがあるのだということを十分に理解して、くれぐれも注意深く取り組んでくださいね。
アクティブ投資は、「投資している感」があり、自分で考えて行動するのが好きな人にとっては非常に面白い分野です。
しかし、必ず儲かる保証はありません。
「失敗しても良い勉強代だった」と思えるくらいの余裕資金で、学びながら進めるというマインドセットで取り組んでいきましょう。
定期的に「ポートフォリオ」を見直す習慣をつける
投資を始めたら、「ほったらかし」か「アクティブ」かに関わらず、定期的にあなたの資産全体(ポートフォリオ)を見直す習慣をつけましょう。
なぜ見直しが必要かというと、市場の動きによって資産の割合が変わってしまったり、あなた自身のライフステージ(子どもの進学、住宅購入など)が変わったりすることで、当初の投資戦略が合わなくなってくる可能性があるからです。
①資産全体に占める各資産クラスの割合
預貯金、ほったらかし投資(インデックス投信など)、アクティブ投資(個別株、暗号資産など)の割合が、自分が想定していたバランスから大きく崩れていないかを確認しましょう。
もし資産の割合が大きく崩れていたら、「リバランス」を検討します。
リバランスとは、値上がりして割合が増えすぎた資産を一部売却し、値下がりして割合が減ってしまった資産を買い増すことで、当初設定した資産の割合に戻すことです。
これにより、リスクを一定に保つ効果があります。
②想定以上にリスク資産が増えていないか
株価が大きく上がった場合など、リスク資産(株や投資信託など)の割合が、預貯金や保険といった安定資産に比べて大きくなりすぎてないかを確認しましょう。
想定以上にリスク資産が増えていた場合、これもリバランスを行う必要があります。
③運用状況は順調か
各投資商品の運用状況(評価損益など)を確認しましょう。
これは、あなたが選択した投資商品が間違っていないか、判断するために行います。
例えば、米国株式に連動するインデックスファンドの評価損益が大幅にプラスであるにもかかわらず、あなたが選んだ個別株やアクティブファンドがマイナスだった場合、間違った選択をしている可能性があります。
なぜ、マイナスなのかについてすぐに調べましょう。
それが一時的なものであると判断できれば、売却する必要はありません。
しかし、株価下落が続くと予想される場合は、すぐに売却しましょう。
損切りとなりますが、諦めも肝心です。
④目標達成までの道のりは順調か
設定した目標(例:10年後に教育資金500万円など)に対して、今のペースで大丈夫かを確認しましょう。
もし、予定より遅れていた場合、積立金額を増やすなどの修正が必要となります。
逆に、予定より順調な場合は、リスクを抑えるために現金や債券などの低リスク資産の比率を上げるなどの修正を行いましょう。
リスクを抑えた運用は、あなたの心に安定をもたらします。
⑤現在のライフステージに合っているか
引っ越しや出産、転職、退職など、大きなライフイベントがあったときは、投資のやり方や資産の配分を見直すことが大切です。
例えば、結婚や出産、引っ越しがあると、家賃や生活費が増えるだけでなく、教育費や住宅購入の頭金、さらに夫婦の老後資金まで考えなければなりません。
そのときには、毎月の積立額を調整したり、持っている資産のバランスを変える必要が出てきます。
リスクを取れる余裕があるなら、株式などの割合を少し増やすのも一つの方法です。
もし、すべてを「現金100%」で持っていた場合には、『現金50%、株式40%、金10%』のように分散しておくと、将来に備えながらリスクも分けることができるでしょう。
目安としては、1年に1回は見直す機会を持ち、大きなライフイベントがあったときには必ず調整するのが安心です。
ちなみに、私の資産配分(預貯金20%、ほったらかし投資34%、アクティブ投資46%)は、少しリスクを取りすぎているため、今年の12月か来年1月頃には割合を調整(リバランス)する予定です。
そもそも「完璧なポートフォリオ」や「正しい資産比率」というものは存在しません。
大切なのは、あなた自身が安心できるバランスを見つけて、定期的に確認しながら、そのときの状況に合わせて柔軟に調整していくことです。
ぜひ、ここまでのステップ1~4を参考にしながら、自分が納得できるポートフォリオを少しずつ作り上げていきましょう。
「ほったらかし」と「アクティブ」投資に関するよくある疑問
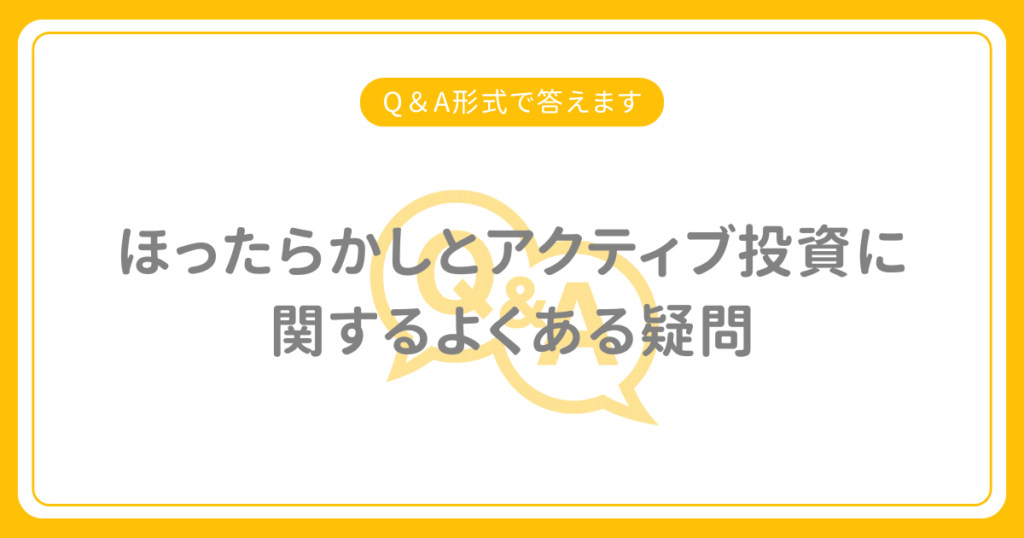
最後に、私自身が投資を始めた頃に疑問に思っていたことについて、Q&A形式で答えていきます。
ほったらかし投資だけで十分では?
はい、十分可能です。
投資初心者の方、仕事・育児で本当に時間がない方にとっては、まず「ほったらかし投資」であるNISAやiDeCoでのインデックス投資信託の積立から始めるのが、最も現実的で合理的な方法だと断言できます。
市場平均並みのリターンで十分満足できる、あるいはそれ以上のリスクは取りたくないということであれば、ほったらかし投資だけでも着実に資産を増やすことは可能です。
アクティブ投資は、さらに上を目指したい、投資自体についてもっと深く学びたいという人が無理のない範囲でプラスアルファとして取り組むものと考えましょう。
アクティブ投資はやっぱり危険?
ほったらかし投資に比べてリスクは高いです。
特に、よく分からないものに一攫千金を狙って大金を投じたり、短期的な値動きに一喜一憂して頻繁に売買を繰り返したりするのは非常に危険です。
ただし、「失っても生活に影響しない少額で始める」「一つの銘柄に集中せず分散する」「長期視点を持つ」「学ぶ」といった対策を取ることで、リスクを抑えることは可能です。
私自身も、個別株や暗号資産といったアクティブ資産への投資は、資産全体の一部に留め、リスクを理解した上で取り組んでいます。
リスクを過度に恐れる必要はありませんが、十分理解した上で自己責任で行うことが絶対条件です。
いくらから投資を始められる?
非常に少額から始められます。
ネット証券の投資信託の積立であれば、月100円から設定可能です。
個別株も、先述の単元未満株サービスを使えば、数百円~数千円から購入できます。
まずは「お試し」感覚で、コーヒー1杯分やランチ代を我慢するくらいの金額から始めてみてはどうでしょうか?
投資のハードルは、あなたが思っている以上に低いですから、ぜひ挑戦してみましょう。
子育て中、時間がないけど投資できる?
はい、もちろんできます!
まさに「ほったらかし投資」は、時間がない子育て世代のためにあるようなものです。
一度設定すれば自動で積み立ててくれるため、あなたの貴重な時間や労力をほとんど使いません。
アクティブ投資に挑戦したい場合も、完璧を目指す必要はありません。
通勤時間や休憩時間、子どもが寝た後の数十分といった「スキマ時間」を賢く活用することで、情報収集や学びの時間を確保可能です。
私自身、毎日時間に追われながらも、スキマ時間を活用してアクティブ投資に取り組めています。
大切なのは「完璧にやろうとせず、できる範囲でコツコツ続けること」です。
損したときが怖いのですが、どうすれば?
投資に「絶対に損しない」という保証はありません。
これは事実として受け止める必要があります。
重要なのは、自分がどれくらいの損失なら精神的に耐えられるか(リスク許容度)を知り、その範囲内で投資額を決めることです。
そして、短期的な価格変動(一時的に含み損が出ること)は気にしないことです。
特にほったらかし投資は、長期で続けることでリスクを抑える効果が期待できます。
もし損をしてしまっても、それは「高い授業料だった」と割り切り、そこから学びを得て次に活かすというマインドセットも大切です。
不安な気持ちに寄り添うパートナーや友人を持つことも、心の安定に繋がりますので、ぜひ関係を構築して頼ってみましょう。
まとめ

今回の記事では、投資初心者の方に向けて「ほったらかし投資」と「アクティブ投資」の特徴と使い分け方法について詳しく解説しました。
本記事の重要ポイント
- ほったらかし投資:インデックス型投資信託の積立で、手間をかけずに安定的な資産形成を実現
- アクティブ投資:個別株や暗号資産で市場平均以上のリターンを狙う、より積極的な投資手法
- 両方の組み合わせ:資産の大部分を「守りのほったらかし」、一部を「攻めのアクティブ」で運用するのがベスト
- 4つのステップ:家計把握→ほったらかし投資開始→少額でアクティブ投資→定期的な見直し
これで「投資を始めたいけど、どの方法を選べばいいの?」「忙しくても資産形成できるの?」という悩みは解決できるはずです。
記事で紹介した方法を実践すれば、子育て世代の忙しいあなたでも無理なく資産を増やし、将来の教育資金や老後資金の準備を着実に進められるでしょう。
次のステップ
まずは新NISAやiDeCoでの「ほったらかし投資」から始めてみることをおすすめします。
月5,000円や1万円といった無理のない金額からスタートし、慣れてきたら少額でのアクティブ投資に挑戦してみましょう。
投資の知識をさらに深めたい方は、以下の記事も参考にしてください。
-
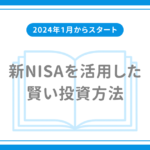
-
新NISAをフル活用!家計を豊かにするための賢い投資方法とは?
「投資って難しそう…」「損するのが怖いな…」 そんな風に思う一方、将来のためには「資産形成を始めなければ…」という気持ちもあるのではないでしょうか。 2024年から始まった「新NISA」は、まさにそん ...
続きを見る
-
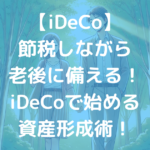
-
節税しながら老後に備える!iDeCoで始める資産形成術!
「iDeCoに興味はあるけど、仕組みが難しそう…」 「本当に始めるべき?」 「市場が暴落したらどうする?」 そんな疑問や不安をお持ちの方は少なくないでしょう。 しかし、今からコツコツと積み立てることで ...
続きを見る
資産形成は一日にして成らず、しかし確実に歩みを進めれば必ず結果がついてきます。
あなたの明るい未来に向けて、今日から第一歩を踏み出してみませんか?
[筆者プロフィール]
40代男性。妻1人、子ども3人(6歳、4歳、2歳)の5人家族。本業年収は300万円前後。2018年1月に貯金500万円から資産形成を開始。約6年で純資産3,150万円を達成(2024年11月時点)。iDeCo、新NISA、投資信託、株式投資、暗号資産などを勉強しながら運用中。過去にハウスクリーニング、現在は暗号資産エアドロップで副収入を得ている。自身の低年収・子育て世代での経験をもとに、再現性の高い資産形成ノウハウやお金に関する思考法・習慣、投資の実践方法、リアルな資産状況などを、同じような悩みを持つ方々の力になれるよう、等身大の言葉で情報をお届けします。
[免責事項]
本記事は、筆者の個人的な経験や見解に基づいた情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入や投資行動を推奨するものではありません。投資には元本割れなどのリスクが伴います。投資に関する最終的な判断は、ご自身の判断と責任において行ってください。また、税制や制度に関する情報は変更される場合がありますので、最新の情報をご確認ください。